
今日は「デトロイト号」を解体調査する日。集まったテクニカルスタッフは、産業用の電気車の整備に20年以上携わってきたベテラン揃いです。早速作業に取り掛かろうとしたところ、またしても想定外の事実に出くわしました。車のボディーの大半が木製だったのです。何といっても90年以上前につくられたクラシックカー。その頃の自動車には、ボディーに木を多用することが珍しくなかったのでしょう。
いきなり面食らったものの、そこは経験豊富なベテランたち。さっそく車の解体作業を進めていきます。前部の座席や床板を外すのは、何だか大工仕事のよう。床板ははめ込み式になっているため、簡単に取り外すことができました。「デトロイト号」が走っていた頃は、きっと、この板を何度も取り外してメンテナンスを行っていたのでしょう。

床板を外して、床下にあるモーター類を取り出します。機械や部品はかなり老朽化しているうえに、配線がすべて切り取られていました。前後に収納されていた蓄電池は、取り出してみると中身は空っぽ。どうやら展示していた「デトロイト号」を見学者に説明するため、ダミーの蓄電池が入れられていたようです。さまざまなパーツを取り外した後で車体を丹念に調べてみると、あちらこちらに亀裂が見つかりました。
取り出した機械や部品は整備したら使えるだろうか。代わりのパーツは見つかるだろうか。昔のように動かすためにはどのような配線にすればいいだろう。さらに、亀裂の入った車体の根本的な補強方法も検討しなければならない。「デトロイト号」復活に向けて、数々の課題が明らかになりました。
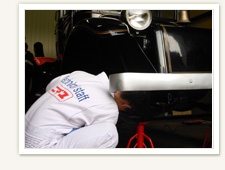
課題が見つかる一方で、面白い発見もありました。日本に輸入されてから改造された跡です。オリジナルの車を知る手がかりとして、GSユアサには1920年(大正9年)の「デトロイト号」の写真とスペックの資料が残されていました。解体調査を行っているのは1917年(大正6年)に輸入されたものですから全く同じではありませんが、資料と比較するといろいろと違いが見つかったのです。
 | まずはブレーキシステム。資料では後輪ブレーキとなっていますが、解体調査では前輪にもブレーキが付けられていることが分かりました。また、写真の車にはバンパーはありませんから、これも日本で取り付けられたものと考えられます。そしてウィンカー。「デトロイト号」のウィンカーは車体の一部を削って配線されており、明らかに後付けです。これらはおそらく、当時の日本の道路事情や法律に合わせて走りやすいように改造されたのでしょう。走行性とは関係ありませんが、車の扉には島津家の家紋が入れられているのも興味を引かれるところでした。 |
| 記録では、オーナーの島津源蔵はアメリカ製のこの車に自社製の蓄電池を搭載して走ったとされています。また、前回の動作確認では、アメリカのインチ(in)サイズのタイヤ回りの修理に、日本のセンチ(cm)サイズの部品を工夫して使った跡が見られました。今回の解体調査でも、さまざまな改造の跡が発見されています。数々の創意工夫が随所に見られる「デトロイト号」。それは、常に新しいものをつくり出そうとする島津源蔵の「開拓者魂」を物語っている車なのです。 |  |

 今日は「デトロイト号」を解体調査する日。集まったテクニカルスタッフは、産業用の電気車の整備に20年以上携わってきたベテラン揃いです。早速作業に取り掛かろうとしたところ、またしても想定外の事実に出くわしました。車のボディーの大半が木製だったのです。何といっても90年以上前につくられたクラシックカー。その頃の自動車には、ボディーに木を多用することが珍しくなかったのでしょう。
今日は「デトロイト号」を解体調査する日。集まったテクニカルスタッフは、産業用の電気車の整備に20年以上携わってきたベテラン揃いです。早速作業に取り掛かろうとしたところ、またしても想定外の事実に出くわしました。車のボディーの大半が木製だったのです。何といっても90年以上前につくられたクラシックカー。その頃の自動車には、ボディーに木を多用することが珍しくなかったのでしょう。 床板を外して、床下にあるモーター類を取り出します。機械や部品はかなり老朽化しているうえに、配線がすべて切り取られていました。前後に収納されていた蓄電池は、取り出してみると中身は空っぽ。どうやら展示していた「デトロイト号」を見学者に説明するため、ダミーの蓄電池が入れられていたようです。さまざまなパーツを取り外した後で車体を丹念に調べてみると、あちらこちらに亀裂が見つかりました。
床板を外して、床下にあるモーター類を取り出します。機械や部品はかなり老朽化しているうえに、配線がすべて切り取られていました。前後に収納されていた蓄電池は、取り出してみると中身は空っぽ。どうやら展示していた「デトロイト号」を見学者に説明するため、ダミーの蓄電池が入れられていたようです。さまざまなパーツを取り外した後で車体を丹念に調べてみると、あちらこちらに亀裂が見つかりました。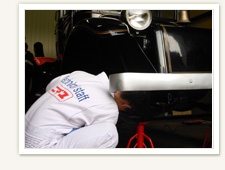 課題が見つかる一方で、面白い発見もありました。日本に輸入されてから改造された跡です。オリジナルの車を知る手がかりとして、GSユアサには1920年(大正9年)の「デトロイト号」の写真とスペックの資料が残されていました。解体調査を行っているのは1917年(大正6年)に輸入されたものですから全く同じではありませんが、資料と比較するといろいろと違いが見つかったのです。
課題が見つかる一方で、面白い発見もありました。日本に輸入されてから改造された跡です。オリジナルの車を知る手がかりとして、GSユアサには1920年(大正9年)の「デトロイト号」の写真とスペックの資料が残されていました。解体調査を行っているのは1917年(大正6年)に輸入されたものですから全く同じではありませんが、資料と比較するといろいろと違いが見つかったのです。


